 |
 |
| |
2014年 全日本ラリー選手権 第8戦 「第42回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ」
|
|
開催日程
|
:
|
2014年10月17日(金) 〜 19日(日)
|
|
開催場所
|
:
|
岐阜県・高山市市 近郊
|
|
主 催
|
:
|
松本カースポーツクラブ(M.C.S.C.)
|
|
競技内容
|
:
|
総走行距離 361.99km / SS(スペシャルステージ)数 10本 / SS総距離 69.82km / ターマック(舗装路面)
|
|
天候/路面
|
:
|
DAY 1 : 晴れ / ドライ DAY 2 : 晴れ / ドライ
|
|
参加台数
|
:
|
53台
|
|
 |
 |
 |
|
総合成績 : 5位 / JN-6クラス成績 : 5位
|
|
SS1
6.13km
|
SS2
6.11km
|
SS3
6.13km
|
SS4
6.11km
|
SS5
6.89km
|
SS6
6.89km
|
DAY1
38.26km
|
|
(3) 4:41.7
|
(2) 4:56.0
|
(2) 4:50.5
|
(5) 4:37.9
|
(4) 5:18.8
|
(3) 5:20.1
|
(6) 30:15.0
|
|
SS7
9.67km
|
SS8
6.11km
|
SS9
9.67km
|
SS10
6.11km
|
DAY2
31.56km
|
|
(4) 6:33.5
|
(4) 4:51.7
|
(3) 6:26.7
|
(2) 4:48.1
|
(3) 22:40.0
|
Total
69.82km |
(5) 52:55.0 |
カッコ内はステージタイム順位。
|
 |
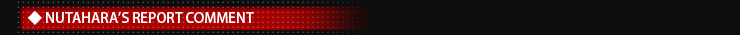 |
 |
 |
前戦のRALLY HOKKAIDOでは、昨年の雪辱を果たして優勝を飾った奴田原文雄選手/佐藤忠宜選手組。全日本選手権のタイトル争いは、ドライバー/ナビゲーターの両部門で、ともに王手をかけた状態で臨んだのが「第42回
M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ」である。
8月末に開催された第6戦の丹後半島ラリーでは、酷暑とまではならなかったものの晩夏の暑さを感じさせていた。それが北海道を経て再び本州にカレンダーが戻ると、飛騨の小京都とも称される岐阜県の高山市は秋の色合いが濃くなっていた。
 再び舞台をターマック(舗装路)に戻した全日本ラリー選手権、今回は2日間で10本のSS(スペシャルステージ)が設けられる。中でも2日目には「あたがす」が新たに設定され、このニューステージが大会最長でもあることからひとつの勝負どころと目されていた。 再び舞台をターマック(舗装路)に戻した全日本ラリー選手権、今回は2日間で10本のSS(スペシャルステージ)が設けられる。中でも2日目には「あたがす」が新たに設定され、このニューステージが大会最長でもあることからひとつの勝負どころと目されていた。
しかし、10月17日(金)に行われたレッキでは、思わぬステージの状況を目の当たりにすることとなる。大会直前に本州を横断した台風の影響により、大量の落ち葉や木の枝などが路面に散乱し、ところによっては一面を覆う状況となっていたのである。さらに「あたがす」は路面が磨かれてスリッピーなコンディションであり、ハイスピードながら難しいSSであるという評判がサービスパークでは語られた。
奴田原選手/佐藤選手組は、本大会で5点以上を獲得すると最終戦を待たずしてチャンピオンとなる。順位だけで言えば4位以上、現実的には2日間それぞれのデイポイントも関わってくるので、条件的にはライバルの勝田範彦選手組に対してかなり有利であることは間違いない。もちろん大会の成績としては優勝がベスト、勝って王座を決めたいというのも偽らざるところであるが、ここは冷静にチャンピオン奪還を最大のテーマとして臨む一戦となった。
昨年に続き、高山市郊外の「道の駅 モンデウス飛騨位山」に設けられたサービスパークから、18日(土)の10時58分にゼッケン1をつける奴田原選手組がスタート。
オープニングはお馴染みの駄吉林道、今年は上り方向で国道158号側からスタートして飛騨高山スキー場へと抜ける。天候は気持ちよい秋晴れ、幸いにレッキでは路面に散乱していた落ち葉も乾いて飛ばされたようで、路面状態は大幅に改善されていた。
SS1「駄吉上り 1 (6.13km)」を勝田選手組、福永修選手組に続く3番手であがった奴田原選手組。続くSS2「アルコピア-無数河 1 (6.11km)」は勝田選手組に続くセカンドベストを刻み、勝田選手組とは8.4秒の差がついたものの2番手でチャンピオン圏内をしっかりキープしている。
しかしサービスを挟んでリピートとなるセクション2で異変は起きた。SS走行中、奴田原選手の耳に届いた異音。それはエンジンルームの中、ターボチャージャーのタービンが発していることを、奴田原選手は即座に理解する。そしてこの異音は、SSを重ねる毎に音量を増し、容赦なく奴田原選手と佐藤選手の鼓膜を揺さぶるのであった。
 Day1、2回目のサービスタイムは20分。この時間内では根本的なトラブルシューティングは不可能、メカニック陣は状況を確認しつつ出来る範囲の対策を施してマシンを再び送り出す。セクション3は6.89kmの牛牧線を2回連続で走行、2本目は日没後のスタートとなるので、ボンネットにはPIAA製の4連ドライビングランプを組み込んだランプポッドが装着された。 Day1、2回目のサービスタイムは20分。この時間内では根本的なトラブルシューティングは不可能、メカニック陣は状況を確認しつつ出来る範囲の対策を施してマシンを再び送り出す。セクション3は6.89kmの牛牧線を2回連続で走行、2本目は日没後のスタートとなるので、ボンネットにはPIAA製の4連ドライビングランプを組み込んだランプポッドが装着された。
牛牧の1回目、奴田原選手組のタイムは4番手。Day1最終の牛牧2回目では3番手に巻き返し、最終サービスに戻った時点では勝田選手組との差は27.2秒と大きかったが、チャンピオン圏内となる2位をキープしていた。
そして最終サービス、チームは不安要素を取り除くためにタービンの交換作業に着手。45分という時間は作業的にギリギリ、あえて言えばアンダーガードが備わるグラベル車よりは作業項目が少ないので、間に合うであろうという判断である。
しかし、残念ながら最終TCに3分の遅着となってしまい30秒のペナルティが加算され、奴田原選手組のDay1は6番手、デイポイントの獲得も幻となってしまった。
19日(日)の朝も快晴の高山地方。気温はグンと下がり、朝6時の時点でサービスパークは2℃と冷え込んだ。パルクフェルメで一夜を明かしたADVAN-PIAAランサー、スタート順は2番手。4B11エンジンに火が入れられ7時01分にパルクフェルメアウト、20分のサービスを経て残り4つのSS、合計距離31.56kmの勝負にスタートした。Day2スタートの段階で、5番手の新井大輝選手組とは11.1秒、4位の福永選手組とは19.4秒差である。Day1のデイポイントがゼロとなっているため、現実的な目標としてはデイ3位で1点とクラス順位で5位の4点、合計5点を獲得することをひとつの指標とした。
注目のDay2オープニングは「あたがす 1」。大会最長のニューステージ、しかしターボを労ることも求められる奴田原選手組は我慢の走りを強いられて4番手タイム。新井大輝選手はセカンドベストで、その差は15.1秒へと拡大。続く本大会4回目の走行となる「アルコピア-無数河」も4番手タイム、新井(大)選手を1.3秒上回ったものの、残り距離は15.78kmあるので逆転は難しい状況と言わざるを得ない。
2本を終えて本大会最後のサービスに戻ったADVAN-PIAAランサー。タイム差を知る観客や関係者の中からも、チャンピオン争いは最終戦に持ち越されるという観測が強まる中、奴田原選手と佐藤選手はチームテントの中でひとつの思いを確固たるものとしていた。
「ラリーは最後まで何が起こるかわからない。他人がどうのこうのではなく、今は与えられた環境の中で自分のベストを尽くして戦い抜くだけだ」
昨年、そして今年のRALLY HOKKAIDOに代表されるように、ラリーは最後まで戦い抜いてみなければ分からないもの。日本、そして世界を戦ってきた奴田原選手、モンテカルロでの日本人初優勝といった栄冠と同時に、多くの悔しい思いも重ねてきている。そうして戦い続けてきたからこそ、ラリーの難しさと怖さ、そして面白さを知っているのだ。
9時57分、ADVAN-PIAAランサーがサービスアウト、いよいよ最後の2SSへと向かう。
SS9「あたがす 2」。背を向けている勝利の女神に呼びかけるかのように、手負いの4B11エンジンが甲高いエギゾーストをこだまさせる。タイムは6分26秒7。勝田範彦選手と新井敏弘選手に続く3番手タイムである。そして、このSS9でドラマは本当の最終章が幕を開けた。4位だった福永選手組がスピンで大きく後退、奴田原選手組はポジションを5番手に上げ、デイ順位も3番手につけたのである。
 5位の得点は4、デイ順位3位の得点は1。合計で5点、このままフィニッシュすればチャンピオンという流れになった。 5位の得点は4、デイ順位3位の得点は1。合計で5点、このままフィニッシュすればチャンピオンという流れになった。
最終ステージはSS8のリピートとなる「アルコピア-無数河」。SS8で奴田原選手組は高山選手組に0.8秒のビハインドを負っており、その高山選手組はDay2のポジションで奴田原選手組の0.6秒後ろとなっており、僅差の最終ステージ決戦を迎える流れとなった。
SS10「アルコピア-無数河」。4回目の走行となるこのステージ、奴田原選手組はこれまでのベストとなる4分48秒1でフィニッシュ。対する高山選手組は4分49秒6、さらにSS9終了時点で0.3秒後ろにいた新井大輝選手組は4分51秒1という結果になり、セカンドベストとなった奴田原選手組が逃げきりに成功。
こちらを振り向いた勝利の女神から微笑みを受けながら、このままマシンをフィニッシュまで運んだ奴田原選手/佐藤選手組。2009年以来5年ぶり、奴田原選手は全日本ラリー選手権の最高峰クラスで自身9回目となるチャンピオンを獲得した。
※チャンピオンの最終確定は、11月28日のJAF表彰式となります。
■奴田原文雄選手コメント
「今年も一緒に戦ってくれたチーム、戦いを支えてくれたスポンサー各位、そして応援してくれたファンの皆さんにチャンピオン獲得の報告を出来ることを嬉しく思っています。
今回は改めて『ラリーは最後まで何が起こるか分からない』ということ実感させられましたね。ただ、ひとつ言えることは何かが起こったときに自分がポジションを上げられる位置にしっかりいるということが大切なのです。だからこそ最後まで諦めることなく走り続けた、それが結果につながったのだと思っています。
次の最終戦・新城は、ヨコハマタイヤの工場があるお膝元の新城市が舞台。チャンピオンとして多くのみなさんに凱旋ラリーをお見せできることが嬉しいですし、来年も見据えてしっかり戦い二年連続優勝を目指していきますので、ぜひ観戦に足を運んでいただきたいですね」
【>> 詳しいレポートはYOKOHAMA MOTORSPORTS WEBSITEをご参照ください】
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
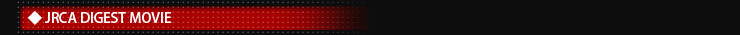 |
 |
|
|
![NUTAHARA.com [HOMEへ戻る]](../../../img/main/head_01.gif)
